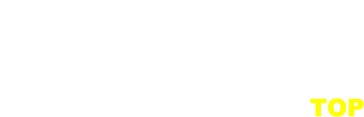稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第161回 「内島康之のチョーチン両ダンゴ釣り」

多くのへらアングラーがそうであるように、マルキユーインストラクター内島康之もまたサンデーアングラーのひとり。普段は営業職で各地を飛び歩き、数少ない週末の休日を大好きなへら鮒釣りを楽しむ時間に充てている。そんな内島を夏の連休が開けて落ち着きを取り戻したウィークデーに、富士五湖のひとつ西湖へと遅ればせながらの夏休みを兼ねた釣行に誘った。とはいえ、あくまで釣りはインストラクターとしてのお仕事。一旦竿を握ればトップアングラーとしての釣技を見せてもらわねばなるまい。自身久し振りの西湖とのことで情報は無いに等しく、スタッフがリサーチした情報を元に安定度ナンバーワンの石切を目指す。午前5時の合図と共に出船した一般アングラーに続き、つり宿 青木ヶ原のマスターに手際よく出船の支度を整えていただいた内島とスタッフ一行は、各々ボートに乗り込みゆっくりと岸を離れた。

パラソル不要!? 涼やかな風に吹かれて釣りを楽しむ〝ヤマ〟の贅沢
先行する一般アングラーの多くが第二出張り方面に漕いでいったことを確認した内島は、邪魔にならないようにと手前の第一出張り先の通称、中平と呼ばれる辺りの岸付けしやすいポイントにボートを留めた。直前の船宿の釣果情報をみると21尺前後の長ザオでのチョーチン両ダンゴ釣りでの釣果が安定しており、良いときで30~40枚/日、平均では15~20枚/日とまずまずの状況が続いているようだ。内島は迷った挙げ句に「比較的空いているので多少短めでもアタリはでるでしょう。」と言いながら、19.5尺を継いで午前6時少し前に実釣開始。

下界では連日最高気温35℃を超える猛暑日に見舞われているが、標高900mに位置する西湖は別天地。早朝の気温が20℃と半袖ではいささか肌寒く、記者は薄手のパーカーを羽織って内島のウキの動きを見つめる。緩やかな風がエメラルドグリーンの水面を吹き渡るが、湖面はほぼベタ凪状態。数投は鮮やかなトップがエサの重さで静かにナジむシーンが続いていたが、何の動きもウキに現われていないにも関わらず、突如小さな泡づけがウキの真横に。これを合図に徐々にウキのナジむ速度に変化が現われ、やがて小さく押えるような動きがではじめる。これに聞きアワセをしながらリズム良く打ち返す内島。すると開始からわずか15分後、ナジミ際に一瞬止めたあと、突っかかりながらナジミきると、すぐにフワリと返し、直後に鋭くチクッと入った。思いのほか早いアタリであったが、遅れることなくこれを捉えると竿が一気に水中へと引きずり込まれる。「これこれ、この引きサイコー!」と言いながら両手で堪える内島。難なくファーストヒットを決め、さぞやノリノリで良い気分だろうと思っていた記者に彼は「早いタイミングで簡単に釣れたときって意外に釣れないことがあるんですよね(苦笑)。」とつぶやいた。

内島にしては珍しく少々ネガティブな物言いだったが、まさかこのひと言が後に現実のことになろうとは……。思いがけずも極度の食い渋りに見舞われた内島は、途中から夏休み気分返上でギアを上げて本気モードの全力エサ合わせに全集中!記者を始めスタッフ一同の注目が集まった。
取材時使用タックル
●サオ
シマノ「飛天弓 閃光PⅡ」19.5尺→後に「飛天弓 閃光L」21尺
●ミチイト
オーナーばり「ザイト へら道糸 フラッシュブルー」1.25号
●ハリス
オーナーばり「ザイト SABAKIへらハリス」0.6号 上55cm(最短50cm/最長60cm)/下70cm(最短70cm/最長80cm)
●ハリ
上下=オーナーばり「バラサ」7号
●ウキ
旭舟「爛」パイプトップ8番→竿を21尺に変更した際は同9番に変更【エサ落ち目盛りはいずれも全11目盛り中8目盛りだし】

取材時使用エサ
両ダンゴブレンド①【内島の基本ブレンドパターン】
「カクシン」400cc+「コウテン」400cc(軽く混ぜ合わせてから水を注ぎ、五指を熊手状に開いて大きくかき混ぜて全体に均等に水をゆきわたらせる)+水300cc+「バラケマッハ」200cc+「浅ダナ一本」200cc
2種の麩材をボウルに加えたら五指を熊手状に開いて大きくかき混ぜ、麩材をまんべんなく混ぜ合わせてダマが残らないよう丁寧にほぐしておく。使うときには別ボウルに適宜取り分け、調整はおもに手水と押し練りで行う。注水の前後に2回に分けて麩材を投入するのはエサの芯をしっかり作るためであり、全麩材を入れてから水を注ぐいわゆる「一緒練り」とは、全体のボソッ気を生かす作り方として使い分けている。
両ダンゴブレンド②【当日の決まりエサブレンドパターン】

「カクシン」200cc+「コウテン」200cc+「凄麩」200cc+「バラケマッハ」200cc+「浅ダナ一本」200cc+水200cc



5種の麩材を軽く混ぜ合わせてから水を注ぎ、五指を熊手状に開いて大きくかき混ぜながらダマが残らないよう丁寧にほぐしておく。仕上がりは粒子感のやや強いボソタッチ。使うときには別ボウルに適宜取り分け、調整はおもに手水と押し練りで行う。なお当日は基エサに近いボソタッチと手水&押し練り調整を加えたヤワネバタッチを打ち分けて、気難しい地べらの食い気を刺激しながら数少ないチャンスを確実にものにしていった【詳細は後述】
内島流 チョーチン両ダンゴ釣りのキモ その一:想像以上に大きな野釣りと管理の釣りの差(違い)をアプローチに生かす!
かつては「〝ヤマ〟の釣りといえば西湖」といわれたように、盛期ともなれば束釣りも珍しくないほどよく釣れたものだが、近年は放流量の減少に加え鵜の食害も加わってか、往時のような釣果は望むべくもない。しかし唯一変わらぬものがある。それは〝ヤマ〟の釣りならではの素晴らしい景観に抱かれながら、ハリ掛かりした瞬間に竿を引きずり込もうとする豪引に耐え、深場から抜き上げてくるダイナミックな釣趣を味わえることだ。今でこそ数は望めないとはいえ、こうした釣趣をこよなく愛する内島は、はやる心を抑えるようにこう切りだした。
「チョーチン両ダンゴ釣りに関しては、私自身野釣りと管理釣り場でその組み立て方に違いを持たせています。おもなポイントとしては、魚影密度の点で管理に劣る野釣りではパイプトップウキを用いてウケ・トメといった動きをだしやすくし、基本的にウキがナジミきるまで(エサがウキの直下にぶら下がるまで)の間に食わせるといった速攻勝負を基本としています。一方で魚影が濃くエサ慣れしたへら鮒が多い管理釣り場では、グラスやPCのムクトップウキを使い、エサをナジませやすくすることに主眼を置いたタックルセッティングで、できるだけウキを深くナジませた位置(エサがタナに入ったところ)で食わせることを意識しています。」

いかに放流量が減ったとはいえ、広大な水域を誇る野釣り場と比べれば格段に魚影密度の濃い管理釣り場では、ある程度リズム良くエサを打ち返していればコンスタントに釣れ続くものだ。しかし西湖のような大きな山上湖では、たとえ意識して早めの打ち返しを心掛けても寄りをキープすることは難しく、さらに必然的に地べら化した良型のみがウキを動かしている今日の状況下においては、本来管理釣り場よりも簡単といわれてきたエサ合わせも、むしろ難易度は高まっているような感じさえする。そこで内島は意図的にアプローチを変えることで、数少ないヒットチャンスをものにできるよう工夫を凝らして実釣に臨んでいるというわけだ。
「数を釣るだけがへら鮒釣りではないと思いますので、無いものねだりをしているだけではなくそれぞれ釣り場に適した攻め方をすれば十分に楽しめるはず。なんといっても猛暑日が続く下界に比べて圧倒的に過ごしやすい山上湖のへら鮒釣りはそれだけでも来る価値十分。しかも数が釣れなくなったとはいえ尺超級のアメ色の地べらを長ザオで深場から引き抜く釣りは、決して管理釣り場では味わえないプライムな時間ですので、ぜひ読者の皆さんにも長竿でのチョーチン両ダンゴ釣りを楽しんでいただきたいと思います。」


内島流 チョーチン両ダンゴ釣りのキモ その二:渋いときほど頼りになる基本軸。ブレずに幅広く、そしてさらに奥深く探る!
開始早々にヒットを決めた内島であったが、その後は弱々しいサワリが現われては消えるを繰り返し、時折でるアタリを逃さずアワセてみるが一向にカウントが進まず八方塞がりの状態に陥ってしまった。こうなると決してガツガツ釣る気持ちはなくとも、マルキユーインストラクターとしてのプライドが〝のんびり夏休み〟など許すはずもない。まずはナジミ際のウキの動きが極端に少ないことから、この日のへら鮒がより深いタナに落ちていないかを探るべく竿を19.5尺から21尺に変更。すると若干ウキの動きは増えたもののエサのタッチに不満があるようで、この日の西湖の地べらは容易に口を使ってはくれなかった。そこで更にハリスを上55cm/下70cmから上60cm/下80cmとし、よりエサの動きにナチュラル感を持たせると同時にエサが動いている時間を長くして、食い渋り気味の手強い地べらの摂餌を促す策に打ってでる。しかしこれにも目立った反応を示さない。万事休すか!
「タックルでの対策をひととおりやってみた結果、あまり良い結果は得られませんでしたので、残すはエサの見直しです。セット釣りに変えるのも一手ですが、変えた直後だけ釣れて以降は釣れなくなるといったことは往々にしてあることですし、せっかく西湖まで来たのですから最後まで大好きな両ダンゴで釣らせてください(懇願)!」
そう言うと、自らが基本とするブレンドとは違うブレンドパターンのエサを複数試し、タッチもカタボソからヤワネバまで、可能な限り幅広く探り始めた内島。すると徐々にではあるがウキの動きに生命感が現われ、決して理想とするパターン化されたウキの動きではないものの、時折でるアタリに積極的にアワせ続けると1枚、また1枚とカウントが進み始めた。そして配達された昼食を摂った後、満を持して仕上げた新たなブレンドパターン(当日の決まりエサ参照)に切り替えて間もなく、突如として力強いアタリがではじめ、ついには連チャンも決めて納得の表情を浮かべた内島。その種明かしは次項にて説明しよう。
内島流 チョーチン両ダンゴ釣りのキモ その三:両ダンゴ釣りのさらなる奥深さを見せつけた、稀有な切り口のエサ使い
さて、この日ターニングポイントとなったエサ合わせだが、最も重要な要因はエサの役割分担を明確に分けたことだと内島は振り返る。どういうことかといえば、本来であれば両バリ共に同じエサを付けて打ち込むだけで釣れる両ダンゴの釣りは、へら鮒を寄せる効果と食わせる効果の両立。すなわち寄せ&くわせのいわば二刀流の役割を担っているわけだが、どうやらこの日の西湖の地べらには一辺倒の攻め方では通用しなかったようだ。記者が改めてここまでの流れを振り返ると、寄せる効果が大きなエサではどうしても食いアタリをだしきれず、かといって食う(アタリがでる)エサではたとえ釣れてもその後長時間サワリすらなくなるという堂々巡りを繰り返してしまっていたことがわかる。
「野釣りでは稀にこうした難しい時合に遭遇することがあります。打開策としてはいくつか考えられるのですが、今回は寄せ効果の大きなエサを打ってへら鮒を引き寄せておき、安心して食うだけの数が寄ったことを示すウキの動きが現われたら一旦そのエサを打ち込むことを止め、食う確率が高い〝好み〟のタッチのエサを打ち込んで仕留めるという手法を採りました。結果的には上手くハマってくれて、時間はかかりましたが良型地べらの強い引きを楽しむことができたので結果オーライとしましょう。改めてヤマの長竿チョーチン両ダンゴ釣り、サイコーですね!」

こうした特別な切り口のエサ使いとして、上バリにボソタッチの寄せエサを大きめに付け、下バリにヤワネバタッチのくわせ系エサを付けるという、いわば〝両ダンゴのセット釣り〟のようなアプローチも有効だという内島。いずれも基エサは同じブレンドのものをひとつ用意するだけで、適宜ボウルのなかでタッチの異なるものを分けておけばいつでも使えるので、セット釣りの用意を忘れたとしても心強い味方となるのでぜひ覚えておきたいテクニックだ。なお忘れてならないのが、この日最終的な決まりエサに加わった「凄麩」の効用だろう。寄せとくわせの両方に効く麩材は数多くあれど、開き・膨らみ・芯持ちといった両ダンゴ釣りに欠かせないすべての特性をバランスよく発揮する麩材は限られる。そうした観点で見ると「凄麩」は汎用性・専門性いずれの面でも高レベルの働きをしてくれる。今回は地味にバイプレイヤーとしての働きを担ってくれたが、影の主役は紛れもなく「凄麩」であろう。

さて相変わらず釣れた後はサワリが途切れるが、すぐさま寄せ効果の大きなエサを4~5投打ち込むとサワリが復活。そしていかにもアタリがでそうな前触れが現われたところでくわせ用として調整したヤワネバタッチのエサを両バリにつけて打ち込むと、サワリながらナジミきったウキがフワッと返してズバッと消し込む。こうしたサイクルを根気強く続けていると、やがて釣れても気配が無くなる間隔が短くなり、最後は十分に寄ったところで一気の釣り込みをみせた内島。「さあ、これから本領発揮」と思われた刹那「ゴロゴロ」と遠雷が鳴り響く。一斉に空を見上げると西の方角に巨大な積乱雲が迫っていることを確認した一行は、後ろ髪を引かれる思いを断ち切り速やかに安全な陸へと上がった。
記者の目【釣果以上の釣趣に酔いしれた〝ヤマ〟のへら鮒釣り】
途切れることなくアタリが続き、いつもコンスタントに釣れる管理釣り場のへら鮒釣りばかり楽しんでいるとつい忘れてしまいがちだが、今回内島が魅せてくれたチョーチン両ダンゴ釣りを目の当たりにすると、元来〝寄せて釣る〟というへら鮒釣りの原点が思い起こされる。かつてへら鮒釣りの黎明期、それほど魚影の濃くなかった山上湖は先達による地道な放流事業により徐々に釣れるようになり、やがて広大な野釣り場でありながら束釣りも可能なほどの魚影を誇った時代を迎えた。しかし時代の流れで放流量が減ると釣果は下降線を辿ったが、たとえ数は望めなくなったとはいえ今でも変わることなく紺碧の水を湛える湖にボートを浮かべ、強い引きの良型地べらとの頭脳ゲームに没頭すると、下界の暑さをしばし忘れると共にへら鮒釣り本来の醍醐味を全身で感じることができる。内島はそんな贅沢な〝大人の遊び〟を知るアングラーのひとり。あくまでへら鮒は生き物であることを十分に理解し、極度の食い渋りに見舞われながらもとっておきの〝奥義〟を繰りだし、大好きな西湖の釣りを満喫したに違いない。盛期の〝ヤマ〟の釣りはまだまだ続く。読者諸兄もひとあし先に秋の休日を、長竿チョーチン両ダンゴ釣りで楽しんでみてはいかがだろうか。