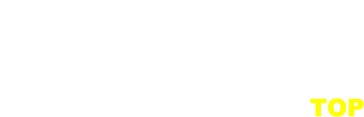稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第160回 「萩野孝之の浅ダナ両ダンゴ釣り」

萩野流浅ダナ両ダンゴ釣りのプロセス(当日の実釣の流れ)
いつでもどこでも鬼のように釣りまくる萩野孝之。へら鮒にとっては〝天敵〟ともいえるこの男の正体は、実はへら鮒の声なき声を聞き分け、難しいオーダーであればあるほど誠心誠意あの手この手を尽くしてへら鮒がエサを食う(釣れる)ことを目指してきた究極のオモテナシアングラー。今回の取材はいわばその集大成。実釣のフィールドは日本一グルメといわれる、口が肥えた大型べらが揃う椎の木湖。最盛期とはいえ混雑する難時合にあえて身を置き、彼の最も得意とする浅ダナ両ダンゴ釣りを紐解いた。先ずは当日の釣りの流れを記しておこう。
■午前6時前に「①基本ブレンド」で実釣スタート。食い渋ることを想定したやや長めのハリスセッティングで始めると数投でウキに変化が現われ、ナジミ際の早いタイミングででるアタリで数枚ヒット。
■予想よりもへら鮒の寄りが早くその動きも活発で、明らかにエサ玉が弄ばれている動きが目立つことから開始20分ほどでハリスを上下10cmずつ詰める。するとアタリの伝達がより明確になり、やがてウキがナジんだところででる強いアタリで〝モーニングサービス〟を確実にものにした。
■10枚ほどヒットさせたところでエサ持ちが極端に悪くなったため、残りエサに「カルネバ」をひとつまみ加えてネバリを増強させるとアタリが復活し4~5枚を追釣。この結果から2ボウル目のエサを「②試行ブレンドA」に変更すると一気にウキの動きが良くなり最初の爆釣モードに突入。
■開始から2時間ほど経過するとへら鮒の食いもひと段落。ややウキの動きに陰りが見え始めるや否や、その原因を「カルネバ」によるまとまりすぎと判断。使用中のエサを小分けして「バラケマッハ」を適宜追い足す。すると復調の兆しが見えたのでひとボウルのエサを打ちきるタイミングで再び「①基本ブレンド」に戻しリスタート。明らかにこのエサの方がウキの動きは良く、しばらくはエサ付けの微調整と振り込みによるエサ持ちのコントロールで拾い続けた。
■さらに1時間が経過するといわゆる中弛みの時間帯に突入し、ウキの動きにまったり感が漂い始め、アタリが激減。エサ付けや振り込みに工夫を凝らしても、ようやくだせたアタリがカラツンになるなど釣況に陰りが見え始める。
■ここでの打開策はエサを開かせた方が良いのか、それともネバリを増してまとまり感を増した方が良いのかを確かめること。まずはこの日まだ本格的に試していなかった開くエサを試すべく「③試行ブレンドB」を手早く仕上げる。このブレンドは決まると大釣りにつながる実績を持つパターンであり、やや長めのハリスで追わせるようなアプローチと組み合わせると威力を増すとのことで、上40cm/下50cmにすると同時にハリも上下ともに「バラサ」7号へとサイズアップ。結果はへら鮒の興味を惹くことができず、むしろそれまでよりも極端にエサ持ちが悪くなったため途中で「GD」を加えてエサ持ちを強化するが、良い結果が得られず当該ブレンドを断念した。
■開くエサはNGと分かったところで、次にここまで最も反応が良かった「①基本ブレンド」に一旦戻したうえでタックル調整に着手。食い渋り気味のへら鮒の摂餌を促すためにハリを上下ともに「バラサ」5号にサイズダウン。軽量化を果たすとともにハリスを上30cm/下40cmに変更するとやはりこちらのエサの方がこの日のへら鮒の好みに沿うようでアタリが復活。しかし肝心なところでエサの踏ん張りが効かないことから、今日はエサの開きが邪魔をしていると確信すると「バラケマッハ」を抜いたブレンドを試みる。こうしてようやくこの日の決まりエサ「④」に辿り着く。
■中盤以降はこのエサを軸にタッチの微調整で釣り込んだ萩野。後半戦になり、明らかにへら鮒の活性が上昇に転じ上層でエサを叩かれ持たない投が目立ち始めると、ハリスを上下ともに5cmずつ詰めてエサ持ちを強化。これにより明らかにウキがナジんでからのアタリは増えたものの、上層で捕えられるアタリがほとんど見られなくなったことから、本来捕えられるアタリを逃している可能性があると判断。ハリを再び「バラサ」6号にするとともにハリスを上30cm/下40cmに戻す。するとこの時間帯にピークに達したへら鮒のオーダーと、萩野が試行錯誤のうえ〝心を込めて〟整えたすべてのセッティングが見事に噛み合い、ダブルヒットを含め怒濤のラストスパートに突入した。

萩野流浅ダナ両ダンゴ釣りの「釣技の真髄」
アタリをだすことすら決して容易ではない現代へら鮒釣り。とりわけ魚体の大型化が極まった管理釣り場における難易度は計り知れない。従って、あえて日本一とも称される大型べらが揃う椎の木湖の、それもソコソコ食い渋ることが予想される祝日の混雑時を狙っての実釣取材を敢行したしたわけだが、萩野の釣りは記者を始めスタッフ一同の予想を遙かに超えた次元にあり、改めて彼の釣りの凄さと奥深さを再認識させられたことに驚きを隠せなかった。何より凄いのは〝今〟釣るために釣行以前から情報収集に勤しみ、目の前にいるへら鮒に〝間違い〟(萩野はへら鮒がハリに付いたエサを食うことをこう捉えている)を起こさせるために今何が必要なのかに全集中すること。研ぎ澄まされた五感に加え、経験値によって培われた第六感も加えたアンテナ(レーダー)を駆使し、その時々のウキの動きをもとにへら鮒の状態を読み解き、声なき声を訊くことに全身全霊を傾けていることだ。そこで具体的にこの日萩野が繰りだした釣技ならびに考え方についてまとめておきたい。
⚫︎直近はもちろん、今年の傾向を含めた釣れ具合やポイント(へら鮒の付き場や動き)、さらには肝心な釣り方やエサの傾向など、釣り場が発信する釣果情報以外にも自らの実釣や釣友から見聞きした情報も加えて緻密に分析した結果、オーダーされた取材テーマを完遂できる釣り座を確保。【当日は二号桟橋奥マス239番】

⚫︎エサ作りをしようとボウルに水を汲んだり戻したりを繰り返しているだけで、桟橋直下に多くのへら鮒が姿を現わしたことを見た萩野は「今日のへら鮒のコンディションはまずまず。サオの長さも規定最短の8尺で十分!」と、たったこれだけのことでへら鮒の状態を見抜き、エサ作りを始めとした初期のセッティングが概ね外れていないことを確信した。
⚫︎へら鮒のレスポンスが鈍いときは必然的にウキが動き始めるまでに時間がかかるが、この日は混雑にもかかわらず5~6投でウキに最初の反応が現われ、その数投後にハリスが張りきる前の早いタイミングでの小さなアタリでファーストヒットを決めた萩野。狙いのタナ1mに完全に寄せきるまでには時間がかかるが、この時間帯はこの早いアタリ(オモリが張りきった直後にエサが自然落下状態になる一瞬の間で食った動き)をだし、なおかつそれを識別してアワせることができなければゼロ釣果で終わる危険性もあるという。
⚫︎萩野自身通い慣れた釣り場であることに加え、直近の釣果情報をもとに混雑時の食い渋りレベルも十分に考慮に入れていたため、釣れ始めてから彼が行ったタックル調整はハリスの長さとハリのサイズ変更のみと実にシンプル。これはいうまでもなくスタート時のセッティング自体が当日の釣況にマッチしていたことを意味するが、こうした高精度のセッティングが無駄を排除し、その後の調整を含めた釣りやすさにつながることを再認識させられた。
⚫︎萩野はある種使い慣れた一定のブレンドパターンで釣りきっていると思われがちだが、記者が知る限りスタート時のエサで決まるケースは極めて稀であり、大抵は基本パターンから始めたうえでこまめな調整を加えつつ、ウキの動きからその日、そのときのへら鮒の嗜好を読み解き、時合の流れに逆らうこと無く1歩1歩目指す釣りに近づくことを旨としている。事実、この日も試したブレンドは4パターンに及び、こうしたプロセスを踏む習慣はナーバスになりがちなメジャートーナメントの決勝であっても変わることがない。いわば、萩野流へら鮒釣りの真髄なのである。
⚫︎真のエサ合わせとは単に正解(釣れる)ブレンドを見つけることではないことを、今回の取材で萩野は実践で示してくれた。肝心なことはへら鮒にエサを見切られない(飽きられない)よう、常に刺激を与え続け、興味を抱かせるエサの開き・動きといった付加価値を持たせることであり、萩野はそれをおもにエサ付けで行っていた。それは彼に解説をしてもらうまでは気づかないほどわずかな違いであった。具体的にはエサが水中を落下していく際に不規則に動くようラフ付け(決して角張らせたものではなく、正しくは「いびつ」といった方が適切かもしれない)を基本とし、ほとんど整った球形や水滴型(涙型)のエサ付けは行わない。すなわち同じエサであってもエサ付け時の形状によって無限に変化をもたせることが可能であり、事実それは1投ごとにルアーチェンジしているかのような効果を生みだしていた。

⚫︎エサの持ち加減はウキのトップのナジミ具合で判断することが多いが、萩野は単にエサを持たせることに重きを置いてはいない。その日一番食うサイズになったタイミングを重視しているため、ナジミ幅だけに頼らず、複合的な要素から食いアタリがでるタイミング判断し、そのアタリを見逃すことなく捉えてヒットにつなげている。サイズというとエサ付け時の大きさだけに囚われがちだが、萩野はウキが立ったときのトメやウケの動き、さらにはナジミ際の上下動のみならず、着水後に沈んでいくエサを追うへら鮒の数や動き、驚くべきはまだ立ち上がる前の水面に寝たままになった状態のウキの微動が起こす波紋や立ち上がり方までも加味して、エサの残量(食い頃になっているか否か)の判断基準としていることだ。
⚫︎「ウキの立つ位置に正確にエサを落とし込む」ことがエサ打ちの基本と教えられ、それを忠実に守り実践している大多数のアングラーにお伝えしなければならないことがある。萩野は決してそのようなエサ打ちを行っておらず、むしろそうしたエサ打ちは投餌点に寄った数多くのへら鮒の無節操な動きによって糸ズレを引き起こし、意図せず複雑化させてしまったウキの動きによって自らの釣りを崩壊させる恐れがあると警鐘を鳴らす。ならば萩野自身はどのようなエサ打ちをしているのかといえば、ウキの立つ位置(基本的には竿掛けの延長線上である自分の正面)の左側(萩野は左利き)にエサとオモリの着水位置が被らないように振り分けて落とし込んでいる。詳しくは動画をご覧頂ければ一目瞭然だが、彼はこれを「L字落とし込み」と称し、寄り具合によってL字の横棒の長さ(距離)を伸ばしたり縮めたりしてスムーズにオモリを沈下させ、それに引っ張られて沈むエサ玉がついたハリスに常に適度なテンションがかかるようにコントロールしている。狙いは確実な食いアタリの伝達にほかならないが、これによりエサがフリーフォールに入った直後のアタリもウキに伝わるようになる。そのヒットチャンスは一般アングラーの倍は優に超えているのではないだろうか。
萩野が食ったと判断し、アワせてヒットさせているアタリの多くは、誰でも識別可能な縦に強く入るアタリもしくは食い上げ(戻し)アタリだが、実は2割ほど記者には分からない(食ったとは判断できない)アタリが含まれていた。それはトメともモドシともいいにくい微細な動きなのだが、その動き(食いアタリ)が先に述べた「エサ玉が食い頃になるタイミング」ででたものであれば躊躇なくアワせてヒットさせていたのだ。

記者の目【日本一へら鮒を釣る男は、日本一へら鮒の声が聞けるアングラー!】
他者を寄せ付けぬ圧倒的な強さから〝鬼〟に形容されることもある萩野孝之。ときにその強さは単なる強引さや自らのフィッシングスタイルをゴリ押しで貫き通そうとする〝我〟と誤認されがちだが、実はこの鬼の正体は100%へら鮒に寄り添うことで正解を導きだそうとする、稀代のアングラーであることがお分かりいただけたであろうか。過去幾度となく彼の釣りを目の当たりにしてきた記者にとっても、今回の取材は目から鱗の〝金言〟が次から次へと登場。特にへら鮒釣りにはテクニック以上に重要な要素があることを示してくれた萩野は、「近年トップアングラーの技量は拮抗しており、ちょっとした気づきやミスによって勝負が決することが多いが、頭ひとつ抜きんでるためにはへら鮒釣りに対する本来あるべき考え方や姿勢を身につけることが必要不可欠!」だと断言する。さらに「へら鮒釣りに必須とされる基本的な所作がいつ、いかなるときでもブレずにできること。小さなことの気づきや観察力。ウキの動きに対する水中イメージや想像力。過去に同じようなことがあったことのフラッシュバック等々が常に習慣づけられていることが肝心!」だとも言い添えた。テクニックに加えてメンタル面の重要性を説く萩野。へら鮒釣りの鬼はこれからも、この奥深き釣りの伝道師として竿を振り続けるに違いない。