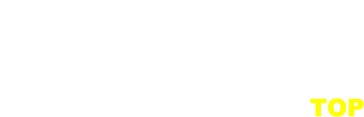稲村順一が徹底レポート「釣技最前線」第160回 「萩野孝之の浅ダナ両ダンゴ釣り」

へら鮒を数多く釣るためには一体何が必要なのだろう。タックル・エサ・アプローチなどのトータルバランス?流行りのブレンドを駆使したエサ合わせテクニック?複雑怪奇なウキの動きを読み解きアタリを選別する洞察力?いずれも欠かせぬ重要な要素であることはいうまでもないが、真に必要不可欠なのは、目の前のへら鮒が今何を欲しているのかを察知し、それに応える対応力にほかならない。それはへら鮒との優れたコミュニケーション能力とアジャスト能力(問題解決能力)とも言い換えられるが、これら全てを兼ね備えているのが稀代の名手、マルキユーインストラクター萩野孝之だ。その優れた釣技は誰しも目にすれば一目瞭然だが、特筆すべきはへら鮒と対峙する際の姿勢(考え方)と、それを形にする実践力だ。今回は埼玉県羽生市の椎の木湖にて、そのあたりを深掘りした取材を敢行。そこで記者が目にしたものは、時々刻々変化するへら鮒のオーダーに必ず応えようとする、100%へら鮒ファーストのオ・モ・テ・ナ・シの精神であった!

取材時使用タックル
●サオ
シマノ「飛天弓 閃光LⅡ」8尺
●ミチイト
オーナーばり「ザイト 白の道糸」1.0号
●ハリス
オーナーばり「ザイト SABAKIへらハリス」0.6号 上25~40cm/下35~50cm
●ハリ
上下=オーナーばり「バラサ」5~7号
●ウキ
一志「Dゾーン」5番【細パイプトップ仕様/二枚合わせ羽根ボディ7.3cm/オモリ負荷量≓1.2g/エサ落ち目盛り=全8目盛り中5目盛りだし】

取材時使用したブレンドパターン4種すべてを使った順に紹介
①基本ブレンド(事前情報をもとに考えたブレンドパターン)
「カクシン」400cc+「浅ダナ一本」100cc+「コウテン」100cc+「バラケマッハ」100cc+水200cc
水を加えて五指を熊手状に開いてザックリかき混ぜ、全体に水がゆきわたったら放置して吸水を待つ。使用する際は小分けしたものに軽く押し練りを加え、まとまり感を増したもので打ち込み開始。エサ合わせはおもに手水と押し練りを加えつつ、時折生麩を加えながらタッチを幅広く探っていく。結果としてはこのエサに特段の不満は無かったが、仕上がりとしては自身80点の評価。さらにへら鮒の活性が高まり動きが激しさを増してきたこともあり、小分けしたエサに「カルネバ」を適宜加えてエサ持ちを強化したところアタリが増えたため、この結果から萩野はさらに高みを目指してエサ持ちを強化した次のブレンドを試す。
②試行ブレンドA(増粘材系のネバリにより開きを抑えたエサ持ち強化に特化したブレンド)
「カクシン」400cc+「コウテン」200cc+「浅ダナ一本」100cc+「カルネバ」50cc+水220cc
作り方は同様。「カルネバ」効果で確実にエサ持ちが良くなり、上層で揉まれてエサを叩き落とされにくくなったことで強いアタリが増加。一時ペースアップが図られたが徐々にアタリが減少傾向に。萩野はこうした変化に至った要因をへら鮒の寄り不足と判断。また増粘材系のネバリが強すぎるとこの日のへら鮒には嫌われる傾向にあることを察知。これらの情報をインプットしたうえで、過去にこうした〝まったり〟時合で幾度となく「バラケマッハ」ベースの開くエサで良い釣りをした経験から次のエサを試すことにした。
③試行ブレンドB(「バラケマッハ」を好む同池のへら鮒に特化した開くタイプのブレンド)
「バラケマッハ」400cc+「浅ダナ一本」200cc+「BBフラッシュ」200cc+水180cc
作り方は同様。開きが良くなることで不安視されるエサ持ち悪化に対しては、ハリのサイズアップ(バラサ6号→同7号)でカバー。またハリが重くなったことで速くなるエサの落下速度に対してはハリスを伸ばす(①のブレンド途中で詰めたハリスを再度上40cm/下50cmに戻す)対策を講じ、食い渋るへら鮒の摂餌欲求を刺激し続けた結果、このエサで決まるときに必ずみられるというウキの立ち上がり直後の止めや突き上げる動きが増えなかったことから、この日のへら鮒は開くエサに対してはそれほど興味がないことを確信。そこで一旦①の基本ブレンドに戻したうえで再度ウキの動きを確かめ、エサ持ちを邪魔している要因が開き(このブレンドの場合は「バラケマッハ」)にあることが分かると、ここまでのブレンド変更を通したプロセスから総合的に判断し、次の決定的なブレンドに辿り着いた。
④この日の決まりエサ(当日のへら鮒の嗜好に的確にマッチさせた◎ブレンド)

「カクシン」400cc+「浅ダナ一本」200cc+「コウテン」100cc+水200cc

作り方は同様。当初80%と感じていたブレンドも「バラケマッハ」を抜くことで開きすぎが解消されるといよいよその真価を発揮。さらに「浅ダナ一本」を増量することで増粘材系のネバリではなく微粒子によるまとまり感(麩材の隙間に入り込んで高密度化するイメージ)が増し、過度に開きを抑えすぎずに適度な膨らみを維持することでこの日のへら鮒の嗜好にマッチ。萩野が試行に試行を重ねた結果辿り着いた好みのエサが目の前にぶら下がると、我先にとたまらず飛びつく。これに対しハリのサイズ、ハリスの長さを最適化すると、さらに無駄に弾かれることのなくなったエサを容易に口にすることができるようになった巨べらが次から次へとハリ掛かりし始めた。